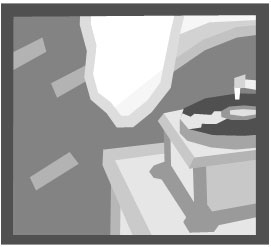
〈交響三章〉は、芥川が東京音楽学校を卒業した翌年、1948年に作曲した作品である。1948年といえば、まだ戦後間もない頃、芥川自身によれば、学校に通うよりも、ヴァイオリンの流しで生活の糧を稼いでいた時代だ。
芥川也寸志は、文豪 芥川龍之介の三男として生まれた。しかし、龍之介は、也寸志が2歳のときに自殺しており、也寸志自身に父の記憶はない。彼にとっての父は、尊敬する存在でありながらも、書斎に掛けられた怖い顔の写真であり、その書斎に置かれていた手回し式の蓄音機であった。
龍之介の音楽趣味については不明だが、そこに置かれていたレコードは、およそ世のクラッシック好きとはかけ離れていた。つまり、ストラヴィンスキーの《火の鳥》、《ペトルーシュカ》やR.シュトラウスの《サロメの踊り》などだ。かくして、年時代から、《火の鳥》を声高に歌う子供が誕生したのだった。
とはいえ、彼の音楽教育は決して早くなく、東京音楽学校にもかろうじて末席で入学したのであった。しかも時代は、戦争へと突き進んでいた。1944年、芥川は陸軍戸山学校軍楽隊に入隊する。これは、当時の陸軍軍楽隊長から学校長に持ち込まれた話で、音楽を志す者を救いたいという気持ちからの集団入隊によるものであった。ここで彼は、テナーサックスをあてがわれ、やがて作曲室に移り、團伊玖磨らと作編曲の仕事に従事する。彼自身、「それまでの実技の習得とともに、この作曲室での作業を通じて得た管楽器の知識が、後にどれ程役立ったか分かりません。」と述懐している。
そうして迎えた終戦。とにかく生きていくために進駐軍のキャンプなどにヴァイオリンを担いで出かけ、バンド演奏に明け暮れた。そんな中、その進駐軍向けのラジオから、近現代の音楽、とりわけソ連の音楽を耳にする機会を得たのである。
《交響三章》の作曲は、このような生活の中猛勉強をし、音楽学校を卒業して放送局の仕事を始めてからであった。初演(NHKによる放送初演)は、1949年9月16日、東京フィルハーモニー交響楽団、自身の指揮による。作風には、戦後、東京音楽学校の作曲科に赴任した伊福部昭の影響を強く受けているといわれているが、既に、のちの芥川スタイルの定番となる「オスティナート(同じ音型パターンの執拗な繰り返し)」の萌芽を見てとる。
第一楽章 Capriccio
ファゴットの4度の伴奏音型に、クラリネットの軽快な旋律が乗る。この旋律は、その後ヴァイオリンで、そしてピアノによって奏でられるが、オーケストラ作品で、このようにピアノを旋律パートとして扱い、さらには、伴奏として輪郭を際立たせるために使用する手法は、ショスタコーヴィチやプロコフィエフを感じさせる。曲はやがて紅潮し、重要なリズム動機に至る。これは、終楽章においても重要な役割を果たす。主題とリズム動機が変奏されたのち、再現部となるが、完全に再現されることなくあっけなくコーダにすりかわり終わる。
第二楽章 Ninnerella
ファゴットによって奏でられる子守唄の旋律が、次々に調と楽器を変え繰り返される。極めて平易なオーケストレーションではあるが、ヴァイオリンにSul Ponticello(駒寄りを奏くことで金属的な音を出す奏法)のトレモロを指示するなど、随所に幼少期に慣れ親しんだサウンドが再現されている。
第三楽章 Finale
リズム動機の再現に始まり、エネルギッシュな旋律がTuttiで奏でられる。この主題は、1~2楽章の旋律の要素が隠されており、終楽章に至って、全曲の輪が完結する仕掛けとなっている。中間部では、プロコフィエフを想起させる後打ちの伴奏を合図に、主題の伴奏音型から派生した半音階的な旋律が躍動する。ここでも、ピアノが重要な役割を演じ、エネルギーを高めたまま最初の主題が再現し、執拗に繰り返されたのち全曲を閉じる。
芥川の作品を聴くと、深刻さとは無縁の楽観主義に満ち溢れていると早合点してしまいがちである。特に、今回取り上げたもうひとつの戦後作品、オネゲルの交響曲第三番との対比はそれを際立出せる。しかし、芥川自身は決して楽観主義者ではなかった。ただ、彼の歩んできた音楽とのかかわりが、音楽をできることの喜びと、それによって生きてきた力強さとは無縁ではないことは間違いない。
彼の音楽に対する姿勢は、現代の音楽を批判する彼自身の次の言葉によってよく表されている。
「― 今日ほど、音楽が専門家の専有物になってしまった時代は、かつてなかったのではないかと思われます。プロの音楽家が作り、提供するものだけが音楽であり、あとの音楽は何か特別な存在である、という風に―。」
芥川也寸志は、無給の指揮者としてアマチュアオーケストラの新交響楽団を育てた。純粋に音楽を愛するが故に演奏するアマオケであるからこそ、彼は惜しみなく支援を続けたのであろう。
(藤井 等)
※ 引用はいずれも芥川也寸志「歌の旅」(初出:読売新聞 1977年)