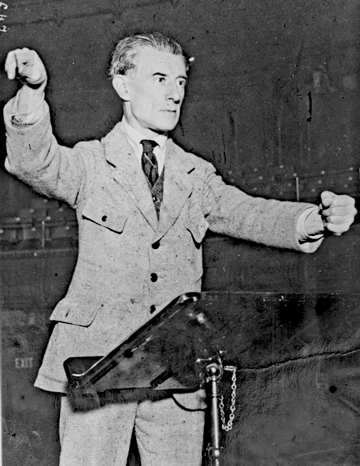 お蔵入りとなったディアギレフとの共同作業
お蔵入りとなったディアギレフとの共同作業
ラヴェルがバレエ・リュスを主催するディアギレフの依頼に応じて作った作品だが、ディアギレフは気に入らず、バレエ・リュスでの上演はお蔵入り。そこで、ラヴェルは独立したオーケストラ曲として発表する。初演は1920年の秋のこと。すでに第一次世界大戦は終結し志願兵として従軍していたラヴェルの兵役もすでに終了していた。
ラヴェルが従軍していたのは1916年3月から1917年6月まで。空軍を志願していたが、実際に配属されたのはドイツと激しい戦いを繰り広げるヴェルダンへの輸送を担う輸送兵、トラック運転手としてであった。入隊の前に、それまで持っていなかった運転免許を取得するといった熱の入れようである。
1855年の宮廷
ラヴェルは、この曲のスコアの冒頭に次のような言葉を寄せている。
「渦まく雲が、切れ目を通して、円舞曲を踊る何組かをかいま見させる。雲はしだいに晴れてゆき、旋回する大勢の人でいっぱいな大広間が見えてくる。舞台は次第に明るくなる。シャンデリアの光はフォルティッシモで輝きわたる。1855年ごろの皇帝の宮廷」。
1855年ごろの皇帝の宮廷というのは、以前にラヴェルが《ウィーン》という作品を構想していたことと繋がってくる。ラヴェルは1906年には既に、ウィンナ・ワルツやヨハン・シュトラウス2世へのオマージュを作曲したいという意思を持っていた。それは実現されることはなく時は進むが、1914年に第1次世界大戦が勃発し、ラヴェルは従軍の準備をするために作曲作業を中断するが、知人に送った手紙によると、その中断した曲の中に《ウィーン》が含まれている。その《ウィーン》と実際に完成した《ラ・ヴァルス》の具体的な関連は不明なのだが、時期的にも《ウィーン》が《ラ・ヴァルス》として完成したと考えても良いだろう。
さて、1855年ごろの皇帝の宮廷というのは、何やらいやに具体的な年の指定だが、何か意味合いはあるのだろうか。19世紀後半から第一次世界大戦の開始時に至るまで、ハプスブルク帝国を治めていたのは皇帝フランツ・ヨーゼフ1世であった。ブルックナーやマーラーをはじめとする、「音楽の都ウィーン」がイメージされる時期のウィーンとハプスブルク帝国を治めていたのは、このフランツ・ヨーゼフ1世であった。フランツ・ヨーゼフ1世が即位したのは1844年、18歳の時。革命で退位した先の皇帝の代わりに颯爽と現れた若き皇帝。実際、フランツ・ヨーゼフ1世は希望に燃えて統治を開始したのだが、その治世の間、ハプスブルク帝国は大国の地位から転がり落ち続けることとなる。その始まりはイタリア統一戦争。1859年、皇帝御自ら戦場に立ち陣頭指揮を行ったにもかかわらず、オーストリアは敗北、領地を明け渡すことになる。それ以降、ハプスブルク帝国は民族独立運動が盛んとなり、皇室の威信は低下する一方だったのだが、1855年というのは、落日が始まる前の、最後の栄光と希望に満ちた時代ということであろうか。
そう考えると、《ラ・ヴァルス》の最後に表現される「崩壊」は、一種の予知夢のようなものなのだろうか。
「飛行機好き」ラヴェルの視点
もう一つ。「渦まく雲が、切れ目を通して、円舞曲を踊る何組かをかいま見させる。雲はしだいに晴れてゆき、旋回する大勢の人でいっぱいな大広間が見えてくる。」というのは、明確に、空からの視点である。空から、だんだんと視点が降りて行ってるのがイメージできる。これは、飛行機の発明により人類が獲得した、それまでには無い全く新しい視点である。この新しい視点を、ラヴェルは迷うことなく曲の基本コンセプトとして採用していることは注目されよう。
そう、ラヴェルが空軍に志願したことを思い出して欲しい。ラヴェルは、飛行機好きであり、飛行機の崇拝者であった。この崇拝者という言葉は、若干、現代ではイメージしにくいものであるが、第一次世界大戦後、飛行機や自動車といった新しい機械は人々と社会を熱狂させたが、芸術家も熱狂させたのだった。この熱狂が、イタリアから「未来派」という一つの芸術運動を生み出す。未来派は絵画・彫刻といった視覚芸術を中心とした芸術運動であるが、音楽家の多くも新しい機械に熱狂したのは変わらなかった。第一次世界大戦後のこの時代、アメリカのジョージ・アンタイルが《バレエ・メカニック》においてプロペラ音を曲の一部として取り入れている。アンタイルとラヴェルの音楽は非常に容貌を異にするが、最新の機械に対する熱狂という点では、相通じるものを持ち合わせていた。
ラヴェルは1933年に発表した「工場に歌を見つける」という短文の中で、「飛行機の交響曲」という一節を設け、次のように書いている。
「生活をこれほどまでに一層快適にし、一層速やかに旅行することを可能にし、今日様々な発見を容易にしている飛行機、それは交響曲にとって何と素晴らしい主題であることか!」別の節の中で「私の《ボレロ》について言えば、私はその構想を或る工場に負っている。いつの日か、私は、大掛かりな工業装置一式を背景に、同作品を上演したく思っている。」
(笠原映子編訳、『ラヴェル著述選集』、法政大学出版局、2025年より)
現在イメージされるラヴェルの姿とは、いささか違う表情を見せるラヴェルではないか。ラヴェルが長生きしていたら、その作風は変わっていったのか?というのはifを語ることでしかないが、そんな、新しい視点を与えてくれる「空からの」視点。次に飛行機に乗るときは、ラヴェルのことを思いだしてみようか。