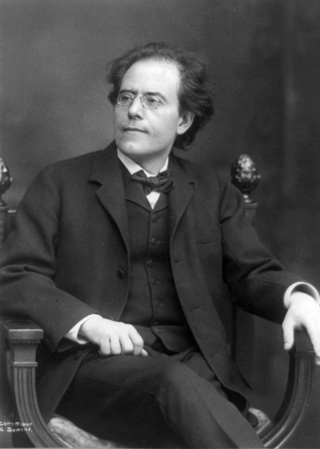 令和のマーラー
令和のマーラー
マーラーをめぐるトピックで、最新の事柄といえばブライトコプフ社が新校訂によるスコアの出版を開始した、ということであろうか。つい先日、ブライトコプフ社の代表が、今年になって出版された交響曲第5番について語るという機会があって出かけて行ったのだが、その内容は驚くべきものであった。
今までの校訂には顧みられることがなかった、生前のマーラーの最終意思が反映された新発見のスコアを新たに今回の校訂に使用しているとのこと。マーラーは、自作の曲を一旦書き上げた後、自分で何度も指揮をして演奏したのだが、そのたびに譜面に手を加え続けていた。そのために、改訂の経緯が非常に分かりにくく複雑なものとなっている。5番はそれが非常に顕著な作品なのだが、ブライトコプフ社の代表であり、かつこのスコアの校訂者であるプフェッファーコルン氏(発音しにくい名であると紹介されていたが)が語るには、今まではパズルの重要なピースが欠けた状態で校訂をしていたが、今回、ついにパズルの最重要ピースが揃った状態になった、と。(非常に細かい話であるが、校訂作業の際に最重要とした資料がもう一つあり、それはマーラーがニューヨーク・フィルにて5番を再演する際に準備していたパート譜への書き込みである。その書き込みは、新発見のスコアがマーラーの手によって完成された後の作業である。しかし、プフェッファーコルン氏が語るには、その再演はマーラーの死によって実現されなかった、マーラーは実際に音にして演奏しその結果として書き込みの採否を判断していたのが常だった、しかしそれがなされていない以上、この再演に向けてのパート譜の書き込みは「マーラーの最終意思」とみなすことはできない、と。)
筆者はこのブライトコプフ新版のスコアを未入手であり、また、実際に演奏された音も聞いてはいないので、現時点で語れることは非常に曖昧な印象論に過ぎないことを予めお断りしておくが、その上で書くならば、細かな箇所の修正は全般的に多岐に渡るものとなり、かつ、数か所はパッと聞いてわかるレベルの目立った音の変更もあるようである(選択式となっている個所もあるとのこと)。おそらく演奏者にとっては、ベートーヴェンの交響曲でのブライトコプフ版からベーレンライター版に変わった時のような衝撃があるのではないだろうか。また、何よりも、マーラー自身の改定の経緯から考えると、「欠けたピース」を揃えた状態、全てが揃ったわけではないが、今まで無かった大きなピースが揃った上で校訂された楽譜は、非常に大きな価値があるものと思う。5番に限るならば、ベートーヴェンの楽譜でベーレンライター版が登場した時と同様の「革命」が起こったと表現して良いと思う。
「5番に限るならば」と書いたが、本日、演奏するのは5番ではなく9番である。では9番はどうなの?ということだが、まず、今回使用するのはブライトコプフ社の新版ではない。9番のブライトコプフ版は一昨年に出版されているが、今回使用するのは、世界的に標準的に使用されているユニバーサル社の国際マーラー協会によるラッツ校訂版である。このラッツ校訂版は1969年のものであり(以降、随時、細かな箇所でバージョンアップが行われている)、国際マーラー協会では近年になって新しい版を次々に出版しているが(6番の中間楽章入れ替え)、9番はいまだ未出版である。そんな中での、ブライトコプフ新版である。
では、その新しい版には5番のような大きな違いがあったのか?ということであるが、それは無いようである。9番は、校訂するにしても他の曲と比べると資料が限定されており、大きな違いを出すのは難しい状態なのだ。前述のように、マーラーは自作を何度も演奏し、そのたびに楽譜に手を加え続けた。そのため、マーラーの最終意思を確定するのが非常に困難となっているのだが、9番をマーラーは演奏することがなかった。マーラーは、9番の初演を準備していたが、突然の死がそれを永久にかなわないものとした。先の、5番の際の、マーラーが再演のためにパート譜に手を入れていたという話を思い出して頂きたい。一旦書いたものを自分で音を出して修正を加える、というマーラーの作曲スタイルから考えると、9番は永遠の未完成作品である。無論、演奏可能な状態には仕上がっており、作曲家によっては、この状態で自分の分の手から離し、あとは演奏者の手に委ねるという作曲者も多いし、むしろそれが一般的である。これは、マーラーが優れた指揮者であったために生じた特殊な事情かもしれないが、9番と、同じく自身の初演が叶わなかった《大地の歌》は、他のマーラー作品とは状況が大きく異なっている。そのため、5番ほどの大きな違いが生じる余地はなく、それがために、演奏者のマーラーの理解度が否応なしに浮き出てくる作品となっている。(ブライトコプフ新版にも細かな部分の見直しによる校訂個所は多数存在し、それらはスコア巻末の校訂報告で確認できることは書き記しておく。)