トロカデロ宮殿のオルガン
 名前の通りオルガン付きの交響曲、である。ここでいうオルガンとはパイプオルガンのこと。建物と一体化した極めて大規模な楽器で、ヨーロッパでは教会に備え付けられることが多く、教会音楽で頻繁に使われてきた楽器である。であれば、この《オルガン付き》も教会での演奏が念頭に置かれたものかというと、そうでもない。コンサート・ホールにオルガンが備え付けられるようになる流れの中でこの交響曲は作曲されている。
名前の通りオルガン付きの交響曲、である。ここでいうオルガンとはパイプオルガンのこと。建物と一体化した極めて大規模な楽器で、ヨーロッパでは教会に備え付けられることが多く、教会音楽で頻繁に使われてきた楽器である。であれば、この《オルガン付き》も教会での演奏が念頭に置かれたものかというと、そうでもない。コンサート・ホールにオルガンが備え付けられるようになる流れの中でこの交響曲は作曲されている。
演奏会プログラムの曲目解説からの抜粋です。
 名前の通りオルガン付きの交響曲、である。ここでいうオルガンとはパイプオルガンのこと。建物と一体化した極めて大規模な楽器で、ヨーロッパでは教会に備え付けられることが多く、教会音楽で頻繁に使われてきた楽器である。であれば、この《オルガン付き》も教会での演奏が念頭に置かれたものかというと、そうでもない。コンサート・ホールにオルガンが備え付けられるようになる流れの中でこの交響曲は作曲されている。
名前の通りオルガン付きの交響曲、である。ここでいうオルガンとはパイプオルガンのこと。建物と一体化した極めて大規模な楽器で、ヨーロッパでは教会に備え付けられることが多く、教会音楽で頻繁に使われてきた楽器である。であれば、この《オルガン付き》も教会での演奏が念頭に置かれたものかというと、そうでもない。コンサート・ホールにオルガンが備え付けられるようになる流れの中でこの交響曲は作曲されている。
 ショスタコーヴィチにとって《ボルト》は依頼による気の乗らない仕事で書いた作品で、オペラ《ムツェンスク群のマクベス夫人》がこの時期のショスタコーヴィチにとって、一番書きたくて最も力を注いだ作品であることは別稿の通り。ここではこの《マクベス夫人》について、ちょっと述べてみることとしよう。
ショスタコーヴィチにとって《ボルト》は依頼による気の乗らない仕事で書いた作品で、オペラ《ムツェンスク群のマクベス夫人》がこの時期のショスタコーヴィチにとって、一番書きたくて最も力を注いだ作品であることは別稿の通り。ここではこの《マクベス夫人》について、ちょっと述べてみることとしよう。
 レニングラード音楽院の卒業制作として作曲した交響曲第1番の大成功によって名を知られる存在となったショスタコーヴィチは、しばらく舞台や映画音楽を中心に活動することとなる。舞台監督や映画監督の要求する音楽を極めて短時間に、しかも高い質で提供することが出来たショスタコーヴィチは、監督達にとって非常に貴重な存在となった。映画音楽はこの後も生涯にわたってショスタコーヴィチが取り組み続けたジャンルとなり、この時期に出会った映画監督のコージンツェフの作品にはショスタコーヴィチは晩年近くになった時期にもタッグを組み、ショスタコーヴィチが音楽を付けたコージンツェフ監督の1971年の作品『リア王』はソ連映画の傑作の一つとして知られている。しかし、残念ながらバレエの分野ではショスタコーヴィチはそのような幸運な出会いを得ることが出来なかった。
レニングラード音楽院の卒業制作として作曲した交響曲第1番の大成功によって名を知られる存在となったショスタコーヴィチは、しばらく舞台や映画音楽を中心に活動することとなる。舞台監督や映画監督の要求する音楽を極めて短時間に、しかも高い質で提供することが出来たショスタコーヴィチは、監督達にとって非常に貴重な存在となった。映画音楽はこの後も生涯にわたってショスタコーヴィチが取り組み続けたジャンルとなり、この時期に出会った映画監督のコージンツェフの作品にはショスタコーヴィチは晩年近くになった時期にもタッグを組み、ショスタコーヴィチが音楽を付けたコージンツェフ監督の1971年の作品『リア王』はソ連映画の傑作の一つとして知られている。しかし、残念ながらバレエの分野ではショスタコーヴィチはそのような幸運な出会いを得ることが出来なかった。
 代表作《幻想交響曲》が最も分かりやすい例であるが、ベルリオーズは詩的・文学的な物語性を音楽に積極的に持ち込んだ作曲家だった。ベルリオーズ自身の文学性は情熱的でヒロイックなロマン主義的なものであり、それはイギリス出身の詩人バイロンに強く影響されたものである。情熱的なバイロンの作品はイギリスにおいて熱狂的な支持を得たが、1820年、バイロンの作品がフランス語に翻訳されて初めて出版されると、それ以来、フランスにおいてもバイロンは非常に読まれる存在となった。1824年にバイロンはギリシャ独立戦争に参加しようとしてギリシャに赴き、その地で死んでしまうのだが、その最後もまた、読者の熱い想いにロマンティシズムを掻き立てるものだった。バイロンは1788年生まれだが、ベルリオーズは1803年生まれなので、この詩人よりも若い世代に属する。ベルリオーズもまたこの詩人に熱中し、『チャイルド・ハロルドの巡礼』という作品に着想を得た《イタリアのハロルド》という作品を作曲している。
代表作《幻想交響曲》が最も分かりやすい例であるが、ベルリオーズは詩的・文学的な物語性を音楽に積極的に持ち込んだ作曲家だった。ベルリオーズ自身の文学性は情熱的でヒロイックなロマン主義的なものであり、それはイギリス出身の詩人バイロンに強く影響されたものである。情熱的なバイロンの作品はイギリスにおいて熱狂的な支持を得たが、1820年、バイロンの作品がフランス語に翻訳されて初めて出版されると、それ以来、フランスにおいてもバイロンは非常に読まれる存在となった。1824年にバイロンはギリシャ独立戦争に参加しようとしてギリシャに赴き、その地で死んでしまうのだが、その最後もまた、読者の熱い想いにロマンティシズムを掻き立てるものだった。バイロンは1788年生まれだが、ベルリオーズは1803年生まれなので、この詩人よりも若い世代に属する。ベルリオーズもまたこの詩人に熱中し、『チャイルド・ハロルドの巡礼』という作品に着想を得た《イタリアのハロルド》という作品を作曲している。
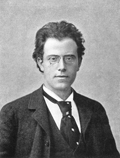 昨年の5月の話となるが、筆者はピアニスト大井浩明氏の《復活》二台ピアノ版の公演に際してプログラムの文章を執筆したのだが、その時の筆者はちょうど引っ越し準備の真っ最中だったため、手持ちの本を参照することが出来なかった。それらはすべて段ボールの中に入ってしまったからである。そのため、この《復活》二台ピアノ版の編曲者であるヘルマン・ベーンについて十分に調べきることが出来なかったという心残りがあるのだが(この時の筆者の文章は大井氏のブログに掲載されている。インターネット上で「大井浩明 復活」のキーワードで検索すると一番最初に出てくるので、ご興味のある方はご覧頂けるようになっている)、そんなことを思いつつ引っ越しも一段落付き書架の整理が終わったところで、整理の終わった書架から何気なくマーラーに関する本を一冊取り出してページをめくったところ、真っ先に「ヘルマン・ベーン」の名前が目に飛び込んできて、ひどく拍子抜けしたのだった。ヘルマン・ベーン。マーラーの伝記の中では特に目を引く最重要人物というわけでは必ずしも無いのだが、ベーンに注目してマーラー関連の書籍を読むと、割と頻繁にその名前が出てくるということに遅ればせながら気がついたのだった。その名前はリヒャルト・シュトラウスとマーラーの手紙の中でも登場し、リヒャルト・シュトラウスと知り合いだったことも分かる。
昨年の5月の話となるが、筆者はピアニスト大井浩明氏の《復活》二台ピアノ版の公演に際してプログラムの文章を執筆したのだが、その時の筆者はちょうど引っ越し準備の真っ最中だったため、手持ちの本を参照することが出来なかった。それらはすべて段ボールの中に入ってしまったからである。そのため、この《復活》二台ピアノ版の編曲者であるヘルマン・ベーンについて十分に調べきることが出来なかったという心残りがあるのだが(この時の筆者の文章は大井氏のブログに掲載されている。インターネット上で「大井浩明 復活」のキーワードで検索すると一番最初に出てくるので、ご興味のある方はご覧頂けるようになっている)、そんなことを思いつつ引っ越しも一段落付き書架の整理が終わったところで、整理の終わった書架から何気なくマーラーに関する本を一冊取り出してページをめくったところ、真っ先に「ヘルマン・ベーン」の名前が目に飛び込んできて、ひどく拍子抜けしたのだった。ヘルマン・ベーン。マーラーの伝記の中では特に目を引く最重要人物というわけでは必ずしも無いのだが、ベーンに注目してマーラー関連の書籍を読むと、割と頻繁にその名前が出てくるということに遅ればせながら気がついたのだった。その名前はリヒャルト・シュトラウスとマーラーの手紙の中でも登場し、リヒャルト・シュトラウスと知り合いだったことも分かる。
 マーラーは1897年(37歳)にウィーン宮廷歌劇場芸術監督に就任。01年11月には才媛アルマ・シントラーと知り合い、後に第5交響曲で使われることになる〈アダージェット〉を捧げて心を射止め、翌年3月に結婚。11月には長女が、04年には次女が誕生した。〈6番〉は、こうした幸福の絶頂期03~05年に作曲され、06年5月27日にエッセンでマーラー自身の指揮によって初演された。
マーラーは1897年(37歳)にウィーン宮廷歌劇場芸術監督に就任。01年11月には才媛アルマ・シントラーと知り合い、後に第5交響曲で使われることになる〈アダージェット〉を捧げて心を射止め、翌年3月に結婚。11月には長女が、04年には次女が誕生した。〈6番〉は、こうした幸福の絶頂期03~05年に作曲され、06年5月27日にエッセンでマーラー自身の指揮によって初演された。