 第1楽章 ロ短調 4/4拍子 ソナタ形式
第1楽章 ロ短調 4/4拍子 ソナタ形式
この交響曲の中核をなす楽章で、[長大な序奏部+アレグロ主部+序奏部の再現+コーダ]のように見えるが、実際にはソナタ形式の原理、それも[第1主題=暗]と[第2主題=明]を対比させてドラマティックに展開していくベートーヴェンの〈運命〉に倣った構造になっている。
 第1楽章 ロ短調 4/4拍子 ソナタ形式
第1楽章 ロ短調 4/4拍子 ソナタ形式この交響曲の中核をなす楽章で、[長大な序奏部+アレグロ主部+序奏部の再現+コーダ]のように見えるが、実際にはソナタ形式の原理、それも[第1主題=暗]と[第2主題=明]を対比させてドラマティックに展開していくベートーヴェンの〈運命〉に倣った構造になっている。
 犯罪者が常軌を逸した化け物に遭遇するというのは、映画でも、古くはヒッチコックの〈サイコ〉や、ホラー映画によくあるパターンだ。この物語も、3人のチンピラが女を囮に強盗を企む、という現実的な犯罪に始まるが、被害者のはずだった役人が、思いもかけない異常な怪物だと判ってくるに従って、攻守が逆転し、非現実的な世界に入りこんでゆく。
犯罪者が常軌を逸した化け物に遭遇するというのは、映画でも、古くはヒッチコックの〈サイコ〉や、ホラー映画によくあるパターンだ。この物語も、3人のチンピラが女を囮に強盗を企む、という現実的な犯罪に始まるが、被害者のはずだった役人が、思いもかけない異常な怪物だと判ってくるに従って、攻守が逆転し、非現実的な世界に入りこんでゆく。
 シベリウスは1865年生まれなので今年が生誕150年のアニバーサリー・イヤーにあたる。《エン・サガ》はシベリウス初期の作品にあたり、1892年に一旦作曲され、その後1902年に改訂された。普段演奏されるのはこの改訂稿であり、本日もこちらで演奏する。同じ交響詩でも、有名な《フィンランディア》(1899、1900)が美しいメロディと力強さに溢れ馴染みやすい音楽となっているのに対し、この《エン・サガ》は、茫漠とした幽玄の世界といった趣であり、途中盛り上がるところもあるが最後は静かに終わる。しかし、シベリウスの確固とした美意識・世界観が強く感じられる作品でもあり、この後に続くシベリウスの作品を予告しているようでもある。
シベリウスは1865年生まれなので今年が生誕150年のアニバーサリー・イヤーにあたる。《エン・サガ》はシベリウス初期の作品にあたり、1892年に一旦作曲され、その後1902年に改訂された。普段演奏されるのはこの改訂稿であり、本日もこちらで演奏する。同じ交響詩でも、有名な《フィンランディア》(1899、1900)が美しいメロディと力強さに溢れ馴染みやすい音楽となっているのに対し、この《エン・サガ》は、茫漠とした幽玄の世界といった趣であり、途中盛り上がるところもあるが最後は静かに終わる。しかし、シベリウスの確固とした美意識・世界観が強く感じられる作品でもあり、この後に続くシベリウスの作品を予告しているようでもある。
 西欧諸国から音楽と音楽家を輸入し、「お雇外国人」の手によって音楽文化を形成したロシア。いわば音楽の発展途上国だったロシアだが、そのロシアが音楽先進国の仲間入りをするためにどうしても必要だったもの、それはロシア人の手による本格的な交響曲だった。多くのロシア人作曲家がその課題にチャレンジしたが、19世紀後半に至って先駆者を遥かに超える高いレベルでその課題をクリアする作曲家が現れた。それがチャイコフスキーである。そのチャイコフスキー最後の交響曲が、本日お送りする交響曲第6番《悲愴》である。
西欧諸国から音楽と音楽家を輸入し、「お雇外国人」の手によって音楽文化を形成したロシア。いわば音楽の発展途上国だったロシアだが、そのロシアが音楽先進国の仲間入りをするためにどうしても必要だったもの、それはロシア人の手による本格的な交響曲だった。多くのロシア人作曲家がその課題にチャレンジしたが、19世紀後半に至って先駆者を遥かに超える高いレベルでその課題をクリアする作曲家が現れた。それがチャイコフスキーである。そのチャイコフスキー最後の交響曲が、本日お送りする交響曲第6番《悲愴》である。
 作曲はスメタナ50歳の1874年~79年。先にI~IIIの3曲が初演され、全6曲の初演は、1882年11月5日アドルフ・チェヒの指揮でおこなわれた。大成功だったが、耳の病いに冒されていたスメタナは、もはや聴くことは出来なかった。曲は、初演の街プラハ市に捧げられており、毎年、スメタナの命日5月12日に国際的音楽祭「プラハの春」の初日を飾って全曲が演奏される。概要は別稿のとおりなので、ここではその補足と、楽曲分析を中心にコメントしていく。
作曲はスメタナ50歳の1874年~79年。先にI~IIIの3曲が初演され、全6曲の初演は、1882年11月5日アドルフ・チェヒの指揮でおこなわれた。大成功だったが、耳の病いに冒されていたスメタナは、もはや聴くことは出来なかった。曲は、初演の街プラハ市に捧げられており、毎年、スメタナの命日5月12日に国際的音楽祭「プラハの春」の初日を飾って全曲が演奏される。概要は別稿のとおりなので、ここではその補足と、楽曲分析を中心にコメントしていく。
今日のゲストは木管のあの人!! ジャカジャカジャカジャカ…………ジャン!
クラリネットの近藤さんです!!!
ヾ(^▽^)ノワーイ!!
お仕事が大変お忙しい時期なのだそうです。が、空気を読まずにインタビューしちゃいました!!!
 サガは、散文で書かれた歴史的な物語のこと。映画「スター・ウォーズ」の冒頭、メインタイトルの音楽をバックに宇宙空間に向かって流れていく文字列は、その典型だ。ワーグナーはウォータンを主神とする北欧神話「エッダ」と、ゲルマンの英雄ジ-クフリ-トを中心にした「ニーベルンゲンの歌」等、様々なサガを素材に4夜に及ぶ楽劇〈ニーベルンクの指輪〉を創作したのだが、シベリウスは他の多くの交響詩と違って、この曲の素材となった物語を明らかにはせず、ただ〈一つの伝説〉とした。
サガは、散文で書かれた歴史的な物語のこと。映画「スター・ウォーズ」の冒頭、メインタイトルの音楽をバックに宇宙空間に向かって流れていく文字列は、その典型だ。ワーグナーはウォータンを主神とする北欧神話「エッダ」と、ゲルマンの英雄ジ-クフリ-トを中心にした「ニーベルンゲンの歌」等、様々なサガを素材に4夜に及ぶ楽劇〈ニーベルンクの指輪〉を創作したのだが、シベリウスは他の多くの交響詩と違って、この曲の素材となった物語を明らかにはせず、ただ〈一つの伝説〉とした。
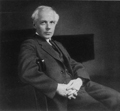 新しい方法論を模索するバルトーク
新しい方法論を模索するバルトークバルトークは無論、クラシック音楽史に名を残す大作曲家であるが、民俗音楽研究家という側面も持っている。そしてバルトークの場合は、この民俗音楽研究が作曲へとフィードバックされたところも大きい。バルトークの音楽は複雑なリズムとどこか奇怪な様相で知られているが、初期のバルトークはそうではなかった。習作にあたる《コッシュート》(1902)は、題材こそ祖国ハンガリーの英雄から取ったナショナリスティックなものだが、その音楽技法はR.シュトラウスばりの「ドイツ的」なものであった(音楽技法を国別に分類すること事態がある種イデオロギー的な視点の産物ではあるのだが)。
コンサート間近!!今日のゲストはトランペットパートから満を持して登場!!
NISHIKIORIサーーーーン!!ヾ(o´∀`o)ノ
コンサートまでもうすぐということで、錦織さんにはちょっとマニアックな質問もぶつけていきます!!
 スメタナの名前は「Bedřich」と書くのだが、これはどう読むのか。「ベドルジハ」というのがカタカナでの一般的な表記であるようだが、実はこの名前、カタカナ表記にするにはかなり無理がある。「r」の上にある逆三角形の記号、これが非常に厄介なのだ。この逆三角形の記号、チェコ語でハーチェクというが、このハーチェクのついた「ř」という文字、クラシック音楽ファンならばどこかで目にしたことがあるかもしれない。
スメタナの名前は「Bedřich」と書くのだが、これはどう読むのか。「ベドルジハ」というのがカタカナでの一般的な表記であるようだが、実はこの名前、カタカナ表記にするにはかなり無理がある。「r」の上にある逆三角形の記号、これが非常に厄介なのだ。この逆三角形の記号、チェコ語でハーチェクというが、このハーチェクのついた「ř」という文字、クラシック音楽ファンならばどこかで目にしたことがあるかもしれない。
お待たせしました!!今夜のゲストはチューバを代表して、井上さんです\(^o^)/イエーイ 代表ってチューバ1人でしたね(;^_^A 1人ならではのご苦労があるようです。
それではインタビューいってみましょう!!(注:この取材は一昨日行いました。)