 英語なら〈ザ・ワルツ〉。このように曲種をそのものズバリで標題にした場合は、作曲年代に注意すべきだ。管弦楽版の初演は1920年12月12日、ラムルー管弦楽団、指揮シュヴィヤール。これが百年前だったら、J.シュトラウスI世とランナーのワルツ合戦に、フランスから “俺のが正真正銘のワルツ” と喧嘩を売っているみたいな自意識過剰なタイトルと受け取られたかも知れない。
英語なら〈ザ・ワルツ〉。このように曲種をそのものズバリで標題にした場合は、作曲年代に注意すべきだ。管弦楽版の初演は1920年12月12日、ラムルー管弦楽団、指揮シュヴィヤール。これが百年前だったら、J.シュトラウスI世とランナーのワルツ合戦に、フランスから “俺のが正真正銘のワルツ” と喧嘩を売っているみたいな自意識過剰なタイトルと受け取られたかも知れない。
演奏会プログラムの曲目解説からの抜粋です。
 英語なら〈ザ・ワルツ〉。このように曲種をそのものズバリで標題にした場合は、作曲年代に注意すべきだ。管弦楽版の初演は1920年12月12日、ラムルー管弦楽団、指揮シュヴィヤール。これが百年前だったら、J.シュトラウスI世とランナーのワルツ合戦に、フランスから “俺のが正真正銘のワルツ” と喧嘩を売っているみたいな自意識過剰なタイトルと受け取られたかも知れない。
英語なら〈ザ・ワルツ〉。このように曲種をそのものズバリで標題にした場合は、作曲年代に注意すべきだ。管弦楽版の初演は1920年12月12日、ラムルー管弦楽団、指揮シュヴィヤール。これが百年前だったら、J.シュトラウスI世とランナーのワルツ合戦に、フランスから “俺のが正真正銘のワルツ” と喧嘩を売っているみたいな自意識過剰なタイトルと受け取られたかも知れない。
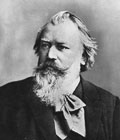 ブラームスは生涯に4曲の交響曲を完成させた。その4曲の交響曲は、ブラームスの同時代から現在に至るまでオーケストラの主要レパートリーとして定着しているが、その中で3番目の交響曲は他の3曲と比べると、演奏頻度が若干低くなる傾向がある。(例えば、ウィーン・フィル、ベルリン・フィル、ニューヨーク・フィル、それぞれある時期の100年近くの間の統計を見ると、4曲の中でいずれも3番が最も演奏回数か少ない。)終楽章はもちろんのこと、全ての楽章が弱音で瞑想的に終わる。演奏時間も他の3曲に比べても短めで、コンサートの最後を熱狂的に締めくくろうとする場合にはいささか不都合だと感じられるからであろう。
ブラームスは生涯に4曲の交響曲を完成させた。その4曲の交響曲は、ブラームスの同時代から現在に至るまでオーケストラの主要レパートリーとして定着しているが、その中で3番目の交響曲は他の3曲と比べると、演奏頻度が若干低くなる傾向がある。(例えば、ウィーン・フィル、ベルリン・フィル、ニューヨーク・フィル、それぞれある時期の100年近くの間の統計を見ると、4曲の中でいずれも3番が最も演奏回数か少ない。)終楽章はもちろんのこと、全ての楽章が弱音で瞑想的に終わる。演奏時間も他の3曲に比べても短めで、コンサートの最後を熱狂的に締めくくろうとする場合にはいささか不都合だと感じられるからであろう。
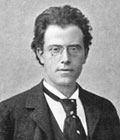 〈葬礼〉が完成した1888年まで時計の針を戻してみよう。28歳のマーラーは指揮者として順調に歩み始めてはいたが、作曲家としては暗中模索状態。20歳の時に作曲した〈嘆きの歌〉で「ベートーヴェン賞」に応募したものの落選。カンタータ+オペラ+交響曲の三要素を兼ね備えた野心作は、保守的な審査には正面から喧嘩を売っているようなものだった。その結果、まず指揮者として生計を立てながら、歌曲で作曲家としての道を模索することになる。後に〈若き日の歌〉として纏められることになる14曲の歌曲(1880~91年)や〈さすらう若人(Gesellen)の歌〉(1883~85年)は、そうした背景から生れた。
〈葬礼〉が完成した1888年まで時計の針を戻してみよう。28歳のマーラーは指揮者として順調に歩み始めてはいたが、作曲家としては暗中模索状態。20歳の時に作曲した〈嘆きの歌〉で「ベートーヴェン賞」に応募したものの落選。カンタータ+オペラ+交響曲の三要素を兼ね備えた野心作は、保守的な審査には正面から喧嘩を売っているようなものだった。その結果、まず指揮者として生計を立てながら、歌曲で作曲家としての道を模索することになる。後に〈若き日の歌〉として纏められることになる14曲の歌曲(1880~91年)や〈さすらう若人(Gesellen)の歌〉(1883~85年)は、そうした背景から生れた。
 20世紀になると歌劇作曲家達は〈ヴォツェック〉、〈ムツェンス郡のマクベス夫人〉、〈イエヌーファ〉等のように、社会の不寛容や閉鎖性によって疎外され、その結果として破局に追いこまれてゆく主人公を描くようになった。〈ピーター・グライムズ〉も、そうした中に含まれる作品の一つである。
20世紀になると歌劇作曲家達は〈ヴォツェック〉、〈ムツェンス郡のマクベス夫人〉、〈イエヌーファ〉等のように、社会の不寛容や閉鎖性によって疎外され、その結果として破局に追いこまれてゆく主人公を描くようになった。〈ピーター・グライムズ〉も、そうした中に含まれる作品の一つである。
作曲は1907~08年、50~51歳。その後1910~11年に〈2番〉を完成、未完の〈3番〉を残して1937年に亡くなっている。初演は08年12月3日、マンチェスターでハンス・リヒター指揮のハレ管弦楽団。空前の大成功だった。
シューマンのオーケストレーションに問題があるというのは、昔から指摘されていたことだが、まずシューマン(1810年生~1856年没。今年は没後150年)の前後で交響曲や管弦楽曲で名が挙がる大作曲家を生年順に並べてみよう。